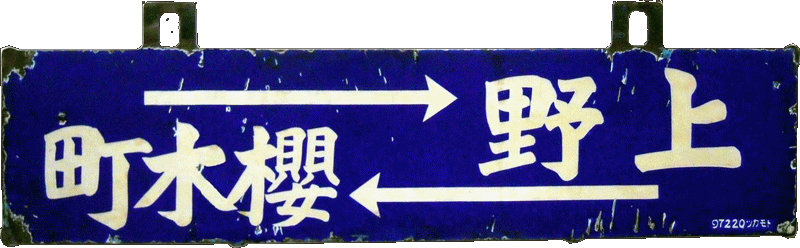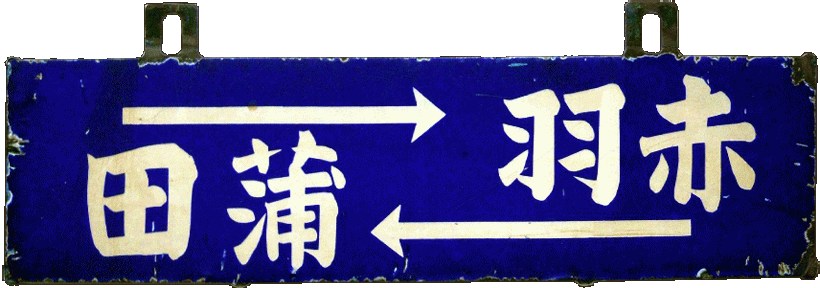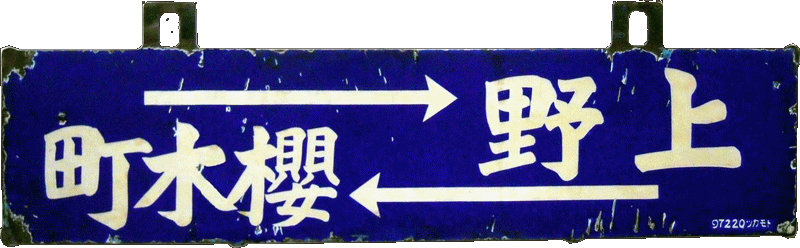
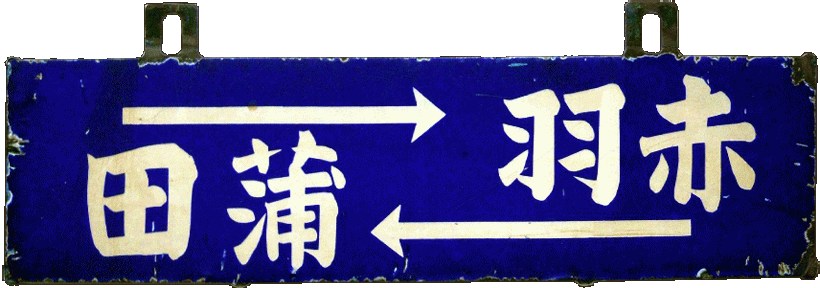
戦前のサボは、右書き(逆文字)筆文字の重厚な物が用いられていました。収蔵するサボの中で一番古いのは国策の「軍需供出」をまぬがれ、
戦後の混乱期を奇跡的にくぐり抜けた京浜線、野上⇔町木櫻・羽赤⇔田蒲の相互式の一枚です。
我が国は日中戦争から太平洋戦争への道を突き進むに伴い時局は悪化し、武器生産に必要な金属資源は不足してきました。この状況を打破
するべく取られた政策が1941(昭和16)年8月30日に公布され、同年9月1日に施行された国家総動員法に基づく「金属類回収令」です。
官民所有を初め家庭の区別なく、金属類の回収が行われました。鉄道関連では機関車に使われていた砲金製のナンバープレートや銘板類、
金属に琺瑯を焼き付けた「サボ」類も、根こそぎ供出の運命に・・・。
琺瑯製広告看板が使われ始めたのは一説には、明治30年代と言われています。鉄道に琺瑯製のサボが導入されたのは、昭和の初め頃。
それまでは木製のサボが用いられていました。
大正時代は下地を白くペンキで塗った物が使われ、昭和に入ってからは黒い下地になりました。
行き先はエナメルにより「平仮名」で書かれて、鉄道工場の塗装職場に数多くいた達筆な人たちの手で製造されていました。
収蔵のサボには1930(昭和5)年に制定された持ちの表記(サボの所属)が無いことと、京浜線が赤羽から大宮まで電化されたのは、1932
(昭和7)年9月1日であることからこのサボが鐵道省御用の塚本製作所で制作されたのは、1929(昭和4)年までの間と推察されます。
四隅と底辺の中ほど2箇所にある突起は戦前に制作されたサボの証ですが、80余年の歳月を経ているにもかかわらず、地色の鮮やかな
青と文字部分の白色にはまだ、艶が残っており、吊り耳もオリジナルの状態を保っています。モハ30系に使われたのでしょう。
なお、鉄道博物館には同種のサボが収蔵・展示されています。
鉄道省から運輸通信省、運輸省を経て国鉄となり、分割され民営化となった我が国の鉄道を見続けてきた一枚の戦前のサボ。
今後、どのような鉄道の栄華盛衰を見届けるのでしょうか。